2021年10月12日(火) 今日は鮎をみんなで食べるということで、まずは二手に分かれて準備開始 熾作りや竹串を作り、鮎の内蔵処理をしたり鮎の焼き方を見たりなど、それぞれ自分の出来ることをしたり、やってみたいことにチャレンジしたり。 最後はみんなで「おいしい!」と言いながら鮎をいただきました byゆたぼん #さつきやま森の学び舎 #オルタナティブ教育
さつきやま森の学び舎Instagramはこちら

さつきやま森の学び舎Instagramはこちら
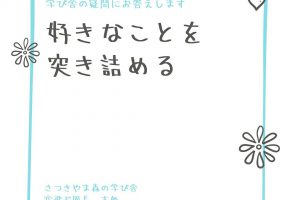
さつきやま森の学び舎Instagramはこちら

さつきやま森の学び舎Instagramはこちら

さつきやま森の学び舎Instagramはこちら

さつきやま森の学び舎Instagramはこちら
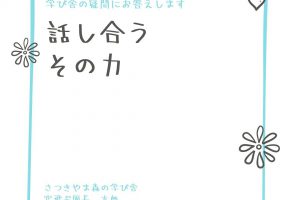
さつきやま森の学び舎Instagramはこちら

さつきやま森の学び舎Instagramはこちら

さつきやま森の学び舎Instagramはこちら
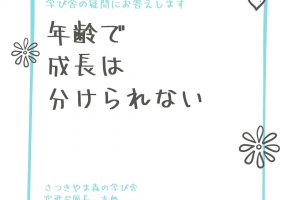
さつきやま森の学び舎Instagramはこちら
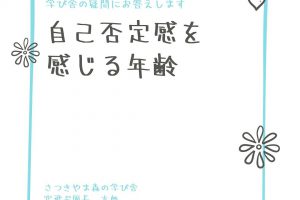
さつきやま森の学び舎Instagramはこちら